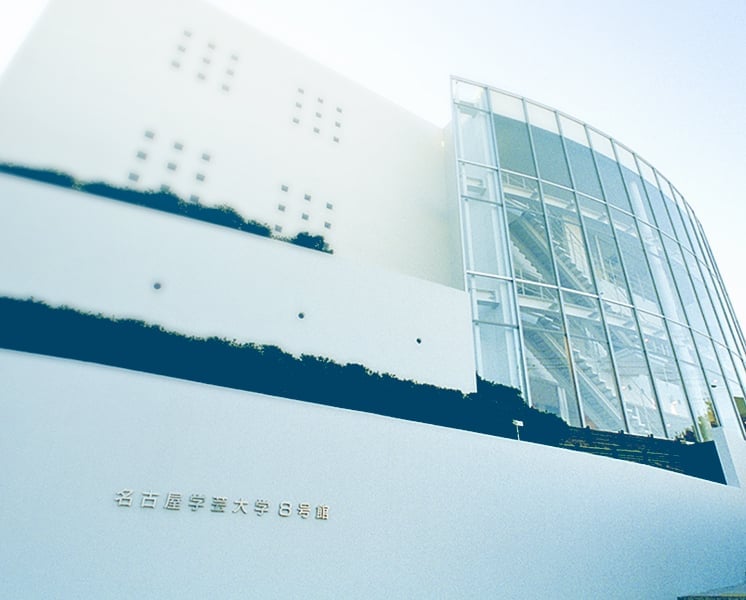
活動の報告Activity Report
学生の活動
2025年度 オーストラリア海外研修④
学びと発見の連続:栄養アセスメント演習とトロピカルフルーツの世界
グリフィス大学の栄養学部の教授と大学院生の方々の講義と施設見学をさせていただきました。講義でははじめに、オーストラリアにおける栄養士資格について学びました。栄養士資格には、「Nutritionist」と「Dietitian」の2種類が存在することを知りました。Nutritionistは、特別な訓練を受けた人や、栄養学に関する学位を持った人、あるいは公認の栄養学コースを修了した人が取得できる資格で、主に健康促進や予防、一般的な食品に関する情報提供などを担うそうです。一方で、Dietitianは、Nutritionistよりも高度な専門資格であり、疾病予防や治療を目的とした栄養管理を行う職種です。Dietitianになるためには、公認の栄養学コースを修了したうえで、実務経験を積み、所定の登録手続きを経る必要があるそうです。
次に、最新の栄養学に関する3つの話題に触れました。まず1つ目は、「野菜嫌いは遺伝的要因による可能性がある」ということです。味覚には、「甘味、塩味、苦味、酸味、うま味」の5つがありますが、中でも「苦味」は、「TAS2R38」という特定の遺伝子のタイプによって感じ方に個人差があるそうです。両親から受け継がれた遺伝子の違いによって、同じ野菜を食べても苦味を強く感じる人とそうでない人が存在すること、野菜嫌いが必ずしも本人の好き嫌いや努力不足の問題ではなく、生まれ持った遺伝的な要因が関係している可能性があることに驚きました。続いて、「ベジメーター」を用いた緑黄色野菜の摂取状況を数値として確認をしました。ベジメーターは、野菜や果物に多く含まれるカロテノイドの蓄積量を、皮膚を通して非侵襲的に測定できる機器です。実際に測定してみることで、日頃の野菜摂取量が数値として「見える化」される点が興味深かったです。さらに、野菜や果物に含まれる硝酸塩の量についても測定を行いました。その結果、人参やバナナに比べて、ビーツに特に多くの硝酸塩が含まれていることが分かりました。硝酸塩は、体内で一酸化窒素(NO)に変換され、血管を拡張することで血流を改善し、血圧を下げる効果などが期待されていることを学びました。
施設見学では、調理室と栄養アセスメントルームを見せていただきました。調理室では、食材の種類ごとに異なる色のまな板が使用しているなど、日本の衛生管理と共通していました。栄養アセスメントルームは、栄養アセスメントの演習を行うための専用の部屋で、外側から学生や教員が中の様子を確認できる作りで、学生同士が実戦形式で演習を行い、それを他者がフィードバックできる環境である点が特に印象に残りました。
その後私たちは、トロピカルフルーツワールドを訪れました。ガイドの方が案内するトラクターに乗車し、園内を観賞したほか、カンガルーなどの動物への餌付け体験、園内で採集された様々なトロピカルフルーツの試食も体験しました。園内にはパパイヤやマンゴー、グアバをはじめ、聞いたことも見たこともない多種多様な果物の木が多数植えられていました。なかでも、豆の状態でしか見たことのなかった「コーヒー」の木が、想像よりも大きく育っていることが印象的でした。

