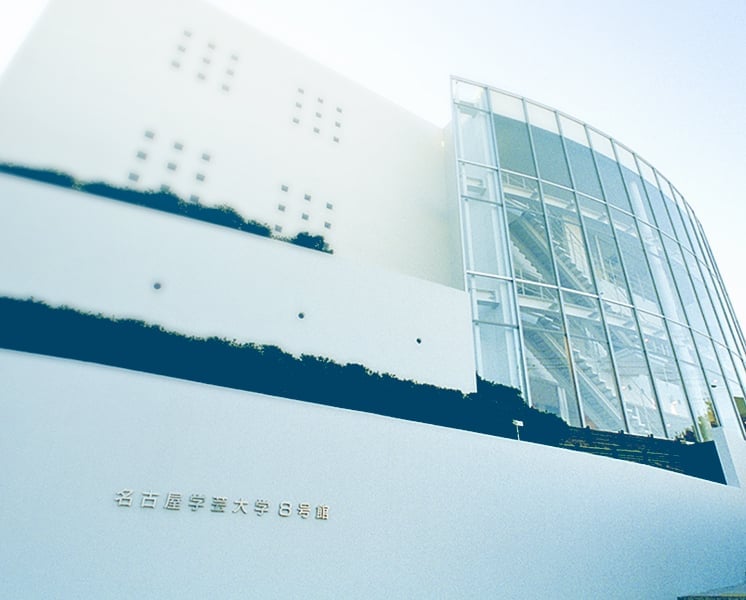
活動の報告Activity Report
学生の活動
2025年度 アメリカ海外研修②
Tour of Tercero Dining Commons
このツアーでは、UCDAVISの食堂の1つを見学しながら食堂の運営や取り組み、力を入れている事などについてお話を聞きました。
ここの学食では、食べ放題の形式をとっており、利用者は自分が好きなメニューを好きな量食べることができます。例えば、下の写真のようにサラダを好みに合わせて食べたり、フルーツも選べたりします。

一方で、下の写真のようにすでに盛り付けられている料理を受け取る形式の場合もあります。この場合でも頼めば好きな量に調節することができます。

メニューは学期がスタートしていれば4週間、夏の間(日本でいう春休みの期間)では2週間でローテーションされています。ディスプレイには9品目(牛乳、卵、魚、甲殻類、木の実、ピーナッツ、小麦、大豆、ゴマ)のアレルゲンが表示されており、日本の8品目(乳、卵、えび、かに、くるみ、小麦、そば、落花生)とは異なることが分かりました。
ここでは、サステナビリティに力を入れていました。取り組みとしては、野菜や果物を大学内で栽培したり、1,000km以内から食材を仕入れるようにしたりなどです。前者は広大な土地があるアメリカだからこそできる取り組みだと思いました。また後者について、東京を円の中心にし半径1,000kmの円を描くとおおよそ北海道と九州が入り、かなり範囲が広いということが分かります。日本では、近くの市町村や県内から仕入れていたらサステナビリティに貢献していると捉えますが、アメリカでは、愛知に住んでて北海道から食材を仕入れてもサステナビリティな取り組みだ捉えているのではないかと考えました。住んでいる土地で取り組みや捉え方の違いが出てくることが分かりました。
またサステナビリティに関連して、「無駄をなくす」という事にも力を入れていました。例えば残食の調査をしたり、利用者の好みの調査をしたりなどです。調査により得られたデータを分析しメニューを決定することで食べられずに残るものを減らしています。さらに、残ってしまったものも燃料やコンポストに利用することで無駄をなくしています。
ツアーを通して、UCDAVISでは、無駄をなくすことやサステナビリティな取り組みには力を加えている事が分かりました。一方で、食べ放題の形式なので食事のバランスや量については、個人の食選択にすべて委ねれていると感じました。必要な栄養素が補えない可能性もありますが、様々な背景を持つ人にとって食を選択できるというのは重要なことであり、サステナビリティにもつながるのではないでしょうか。


