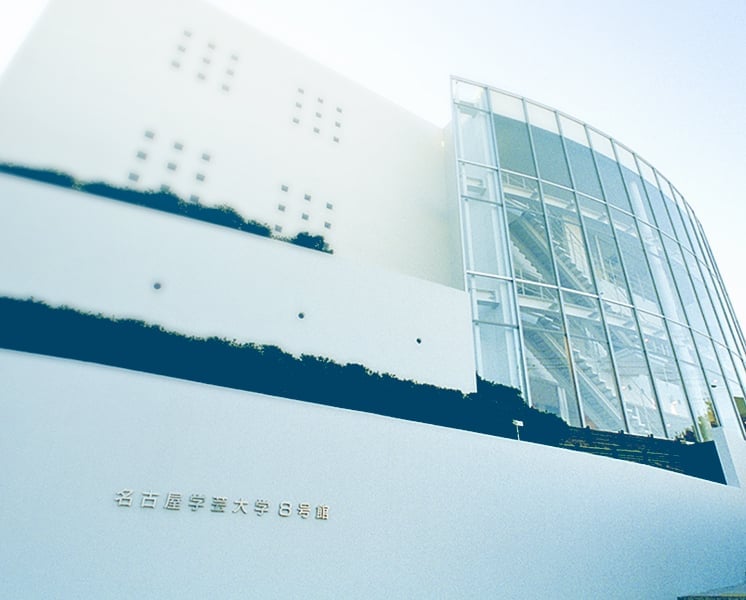
活動の報告Activity Report
その他
第11回 栄養教諭育成研究会を開催しました。
2月15日(土)に名古屋外国語大学 名駅キャンパスにて、第11回栄養教諭育成研究会を開催しました。
現在、愛知県・名古屋市・岐阜県・三重県を中心に全国で本学の卒業生が栄養教諭・学校栄養職員として100名以上活躍しています。
今回も卒業生35名、1~4年生の在学生32名(4月から栄養教諭・学校栄養職員として働く学生7名含む)が参加しました。
【第1部】食育教材(ノウカサバイバー)体験会
本学では学部連携で食育推進全国大会参加や食育教材作成を行っています。
ノウカサバイバーは、学生が開発した、「作物」「農具」「肥料」の三つの基本カードを使って農場を経営してお金を稼ぐゲームです。環境を無視した農場経営をすると環境破壊でゲームオーバーになってしまったり、離職や猛暑などランダムなイベントによって、突然の不運に見舞われたりする、スリルある展開を楽しめるゲームです。
3年生教職課程履修学生がゲームマスターとなり、卒業生にゲーム体験をしてもらいました。

卒業生からの感想の一部を紹介します。
・ゲームで楽しみながら、自然と環境や農業問題について学べて上手く活用できれば良い教材になると思いました。
・「地球の限界」が全員共通して蓄積するのだと目に見えるので、子どもたちがプレイする時、環境問題は地球みんなの問題だと気づくことができて良いと思いました。
・福祉施設など大人が楽しめる場面でも活用できそうだなと思いました。
【第2部】昼食・座談会
卒業生と教職員が昼食をとりながらの座談会で、交流を深めました。

【第3部】講演会と事例報告
第3部からは卒業生に加え在学生も参加しての会です。
第11回のテーマは「学校給食における地場産物の現状と地場産物を活用した食に関する指導」です。
第4次食育推進基本計画では、子供たちへの教育的な観点から、栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の取組を増やすことが数値目標として掲げられています。
気候変動などによる農作物の生育状況が不安定で高騰していたり、労働者不足や社会構造の変化から食品の製造や供給がこれまでと違ってきたりする現状における「地場産物を活用した食に関する指導」について、みんなで学び検討したいと考えて設定したテーマです。
講演:学校給食における主食や地場産物のサプライチェーンの現状
公益財団法人 愛知県学校給食会 理事長 高橋 伸至様から、講演をいただきました。
多くの資料を準備していただき、具体的なデータを示しながら、主食の提供に関わる現状をお話いただきました。

学生の感想一部紹介
・食品の流通の部分を詳しく知ることができたことで、献立を立てる際には栄養素だけでなく、関わってくださる方のことまで考える必要があることを改めて実感することができた。
・献立作成には、栄養面や食育、予算の面だけでなく物資の供給の存続のために計画的に主食を選定したり、地場産物を活用したりする必要があると学びました。
卒業生の感想一部紹介
・米飯給食を中心に、時々パンや麺を入れてバラエティ豊かな献立を作成することが当たり前になっていましたが、主食の現状を知り、物資を供給する立場になって考える視点ももたなければいけないと思いました。
事例報告:地場産物を活用した食に関する指導
豊田市逢妻中学校(兼務先 豊田市中部給食センター)に勤務する卒業生の鈴木基己先生から事例報告をしてもらいました。
地場産物の活用実態や活用状況を児童生徒や保護者・教職員に知らせる手立て、活用した地場産物の指導の方法や作成した指導資料の学校での活用状況調査結果など、具体的な事例報告の後、栄養教諭として働いている卒業生から多くの質問があり、それぞれの働く地域での課題解決についての検討に向けた時間となりました。

学生の感想一部紹介
・栄養教諭の現状を知れて、すごく現実的に考えられた。より栄養教諭を知りたいと思いました。
卒業生の感想一部紹介
・真似してみようと思う内容が盛りだくさんでした。大変勉強になりました。来年もぜひ参加したいです。
・自分の働く市でもできそうなことはないかな?と改めて考え直すことができました。今日学ばせていただいたことを持ち帰って、これからの業務に生かしたいです。
・来年度はもっと地場産物の指導に力を入れたいなと思いました。他の先生方に渡す指導資料は作ったことがないので取り入れていきたいです。
【第4部】情報交換会
前半は卒業生と在学生での懇談や情報交換会、後半は卒業生同志での情報交換会を実施しました。

学生の感想一部紹介
・実際の現場で働かれている先生方の貴重なお話を聞けた。より一層同じ現場で働きたいと強く思った。
・先輩からたくさん話が聞けて、栄養教諭にもっと興味を持つことができました。とっても有意義な時間になりました。
・毎年参加していますが、3年生で参加した去年とはまた違った気持ちで参加出来たように思います。春から自分も栄養教諭の1人として働くのだと思うと、先輩方が実践されていることは本当にすごいなと感じましたし、先輩方の卒業年に関係なく仲が良く楽しそうに話している姿に安心しました。
卒業生の感想一部紹介
・地域や学校種など置かれた環境が異なる中で、参加者の皆さんそれぞれが頑張っていることがわかり、明日からの励みになりました。
・栄養教諭の職務に悩みながらも、前向きに歩み続けてみえる若手栄養教諭の姿に頼もしさを感じました。と共に当たり前ですが、経験年数によって悩みの質も異なることを認識しました。
・学生が栄養教諭になることを夢見ているのを全力で応援したいです。学生の熱意を見て、仕事への情熱がさらに燃え上がった感じがしました。
・大ベテランの栄養教諭の先生とお話ができたのが嬉しかったです。
※今年度から、学部卒業生の栄養教諭に加え、大学院卒業生の栄養教諭にも参加していただきました。
「学生と卒業生でもっと話がしたかった。」「卒業生同志でもっと情報交換したかった」など、時間が足りなかったと感じた感想もありました。学生の学年の違い、栄養教諭の経験や学校種・地域の違いなど、それぞれの課題に対して今後も工夫をしながらこの研究会を続けていきたいと思います。

